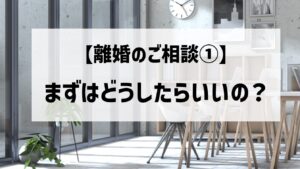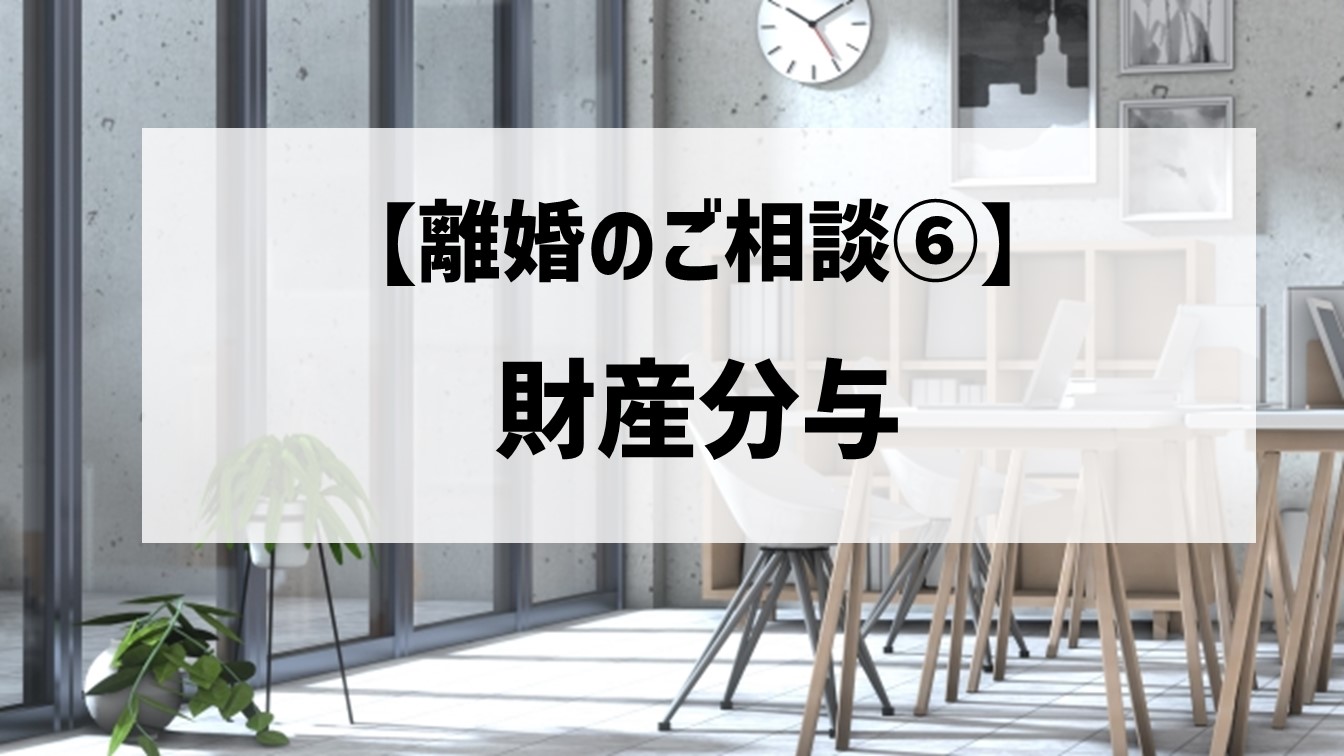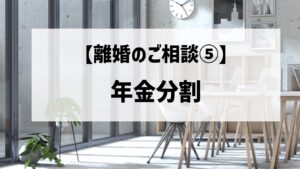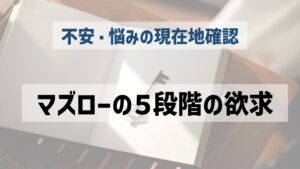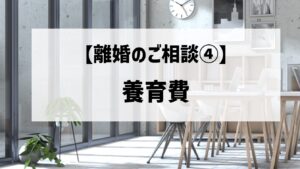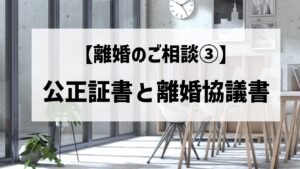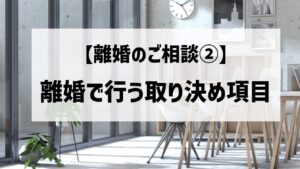結婚した3組に1組が離婚しているという統計もありますが、離婚のご相談も多くあります。
「熟年離婚」や「卒婚」と言われる定年前後での離婚のご相談も多く、やはりメインは「財産分与」のお話になります。粛々と進めていきたいご意向の方がほとんどで、FPの私からは財産分与についての手続きや税制に関する情報提供と交通整理がメインです。
重大な関心事のメインとして「税金」があります。民法での解釈をベースとして、不動産取得税、贈与税と取り扱いが異なります。
今回は「財産分与」の概要について基本的な考え方を解説します。
財産分与とは
財産分与とは、相手方の請求に基づき、離婚した者の一方から相手方に財産を渡すことをいいます。
(民法768)
夫婦の財産の分類
民法では下記のように財産を分類しています。
民法第762条「夫婦間における財産の帰属」
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
- 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
- 1.実質的に「夫婦どちらかの財産」または「夫婦の共有の財産」
-
実質的にどちらかの財産を、相手に財産分与する場合は不動産取得税の対象となります。
- 2.名義は夫婦どちらかの名義となっているが、婚姻中の夫婦の協力により取得されたものであり、実質的には共有と考えられるもの
-
婚姻中の財産を清算する趣旨でこのような財産を分与する場合は、形式的に財産権の移転が行われることはあっても所有権の帰属を確認する趣旨にすぎません。なので、実質的な財産の移転には該当しないので不動産取得税の対象にはなりません。
財産分与の目的
財産分の目的は次の3つに分類されます。
- 財産の清算
- 慰謝料的財産分与
- 扶養のための財産分与
- 1.財産の清算
-
前段の「名義は夫婦どちらかの名義となっているが、婚姻中の夫婦の協力により取得されたものであり、実質的には共有と考えられる財産(民法762②)」を、所有権の帰属を確認(清算)するために行う財産分与です。
- 2.慰謝料的財産分与
-
慰謝料を払う現金が不足するなどの場合に、不足額を調整するために行う財産分与です。
- 3.扶養のための財産分与
-
離婚後の配偶者の扶養のために行われる財産分与です。
2と3は、分与を受ける側が「慰謝料や扶養料に相当する財産の取得」とされるために、不動産取得税の対象となります。
財産分与と贈与税
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
贈与税がかかる場合
次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
- 1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
-
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
- 2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
-
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
不動産の財産分与
離婚後に不動産の財産分与を行うと「譲渡」となります。
分与した人に譲渡所得の課税が行われ、分与を受けた人はその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
離婚前に「生前贈与」で財産分与を行うこともできます。
「譲渡」と「生前贈与」では評価方法や税制の取り扱いが違うので、慎重に検討する必要があります。
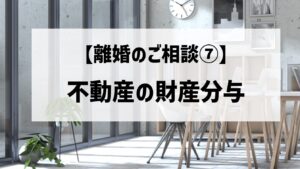
離婚における財産分与請求権の時効
離婚後2年以内に申し出ないと消滅してしまいますのでご注意ください。
(財産分与)
民法768条 財産分与
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
退職金は財産分与の対象になる?
退職金は、財産分与の対象になり得ます。
「退職金は賃金の後払い」というのが現在までの主流的な考えとなっているため、婚姻期間中に給料を貯めた預貯金とみなすことができます。そうすると退職金も「離婚時における財産分与の対象と言えます。
しかし、昨今では退職金は将来もらえるかどうか不確かで、倒産やリストラなどで退職金が支給されないケースも考えられます。
裁判所では「将来の退職金については、近い将来に受け取る可能性が高い場合には財産分与の対象となる」という判断がされています。
定年退職が間近に迫っており、退職金の確定額が見込まれるような場合に認められるようです。
退職金が既に支払われていて手元に残っている場合は、婚姻期間分の退職金が財産分与の対象になります。
FP相談の現場から
離婚のご相談については、揉めている場合は弁護士しか関わることができません。
FPのところへ離婚のご相談に来られるケースは、財産分与について双方で納得しており、粛々と進めていきたいご意向の方です。
公正証書や離婚協議書の作成は、司法書士や行政書士に依頼することになりますが、その前段階の財産分与について税制を含めた金額的なものを明らかにしたい場合にまずはFPを尋ねられるといった流れです。
「いきなり弁護士や司法書士、税理士を尋ねるのはハードルが高い」といった方も多く、ファーストコンタクト(最初の入り口)としてFPにご相談に来られる方も多いのでお気軽にお尋ねください。