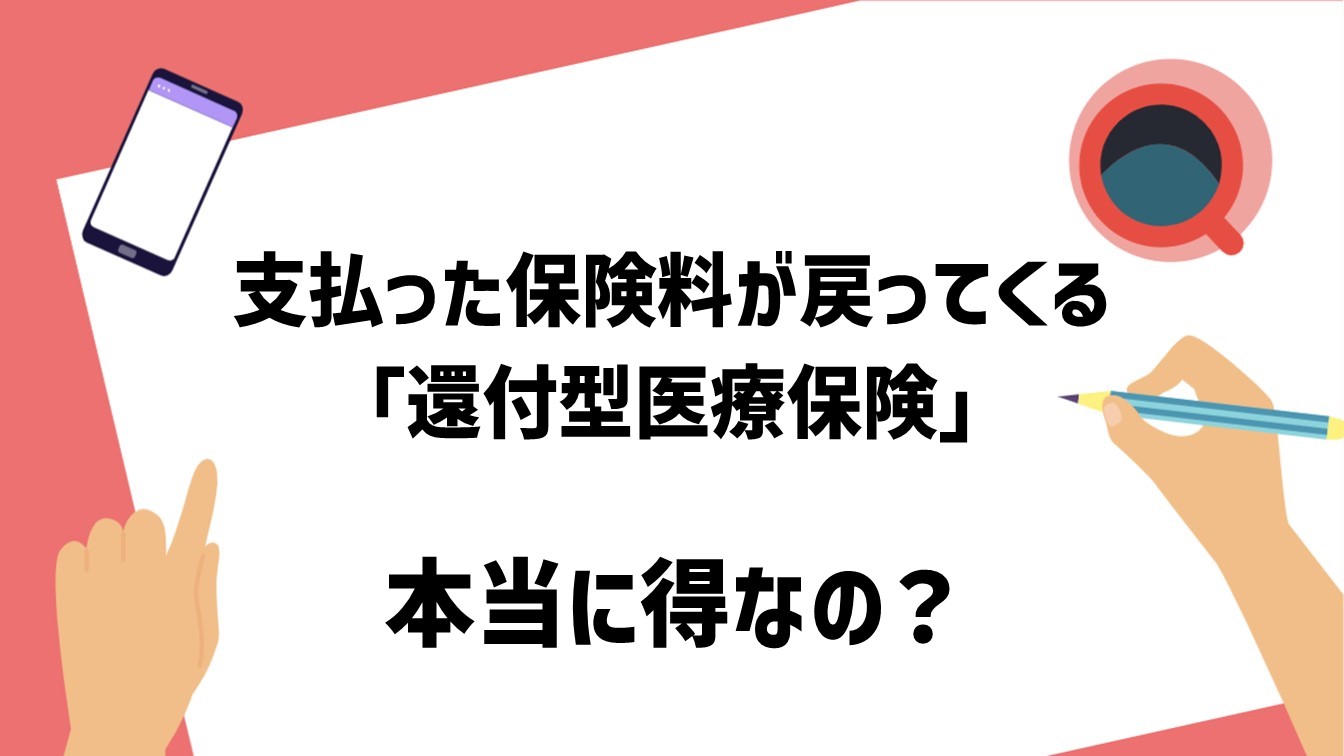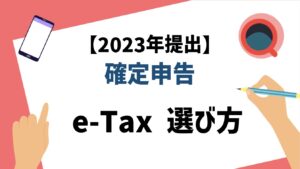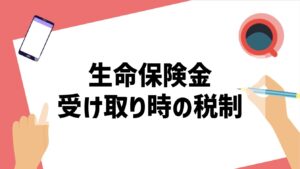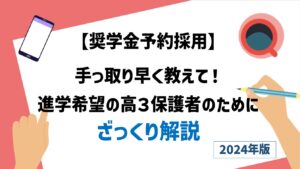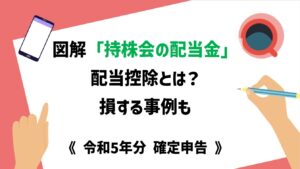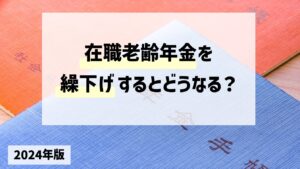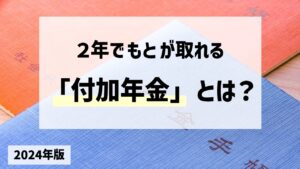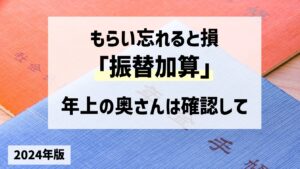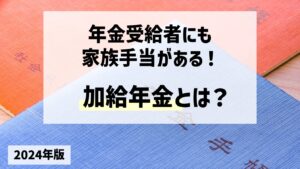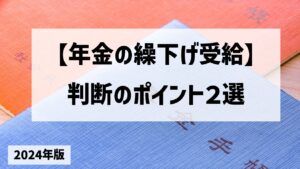医療保険の中には、支払った保険料が戻ってくる「還付型」という医療保険があります。
あらかじめ決められた年齢に達した時に、それまで支払った保険料が返還されるという医療保険です。(健康祝金や生存還付金、ボーナスなどの還付金の名前があります)
それまでに保険の給付を受けた場合は返還額から差し引かれますので、支払額より給付額の方が多ければ返還額はありません。しかし、返還される保険料がある場合は「掛け捨て」でなくなるということから人気のある医療保険です。
還付型・掛け捨て 医療保険比較
2023年5月現在販売されている医療保険のなかから、還付型医療保険と掛け捨て医療保険をそれぞれ抜粋してシミュレーションをしてみました。
- 30歳男性
- 健康体
- 保険期間終身
- 保険料払込満了60歳
- 入院日額5000円(1入院につき60日まで、通算支払限度日数1,095日)
- 手術給付金 外来手術2.5万円、入院をともなう手術5万円
- 先進医療給付金 通算2,000万円
| 還付型医療保険(A社) | 掛け捨て型医療保険(B 社) | |
|---|---|---|
| 月額保険料 | 3,379円 | 1,917円 |
| 60歳までの総支払保険料 | 1,216,440円 | 690,120円 |
| 60歳時の還付額 (保険給付ナシとして) | 1,175,400円 | ー |
| 差引総支払保険料 | 41,040円 | 690,120円 |
月額保険料は、還付型3,379円、掛け捨て型1,917円で、掛け捨て型医療保険の方が1,462円少ないです。
しかし、60歳まで入院などの保険給付を受けなかった場合の総支払保険料は、還付型41,010円、掛け捨て型690,120円で還付型医療保険の方が649,080円少ないです。
保険給付を受けなかった場合は、還付型医療保険の方が「総支払保険料が少なく済む」と言えます。
保険料差額を運用した場合のシミュレーション
前の比較シミュレーションで出した還付型医療保険と掛け捨て型医療保険の保険料差額1,462円を、毎月投信積立で30年間運用した場合をシミュレーションしてみました。
| 年利1%運用の場合 | 613,496円 |
| 年利2%運用の場合 | 720,365円 |
| 年利3%運用の場合 | 851,961円 |
還付型と掛け捨て型の総支払保険料差額は649,080円でした。
月額保険料の差額1,462円を毎月投信積立で年利1%として運用した場合、613,496円となりました。
還付型と掛け捨て型の総支払保険料差額は35,584円となり、ほぼ変わらないくらいになります。
年利2%、3%になると、積立運用した方がお得になる計算です。
投信積立は元本より減ってしまうリスクもあるので確定的なことは言えません。
しかしながら「つみたてNISA」を経験したことのある方ならば、20年以上の長期運用で年利3%の運用が不可能ではないことはご理解いただけると思います。
これ見て掛け捨て型医療保険を選択したたものの、還付型医療保険との保険料差額を積立運用しないで日々の生活費に使ってしまうと「還付型医療保険を選択した方がお得だった」ということになりかねません。
還付型医療保険は、保険料に貯蓄が内包されているので、保険料の引き落とし時に必ず貯蓄がされるという「拘束力」がメリットなのかもしれません。
では「還付型医療保険と掛け捨て医療保険のどちらを選んだらいいのか」について、考えるポイントを次にまとめてみました。
ポイント1「保険給付分は還付額から差し引かれる」
入院などの保険給付があった場合はその分還付額から差し引かれます。
入院などなく全く給付を受けなかったら予定した額が還付されるので、健康維持のモチベーションになるかもしれませんね。
しかしながら保険給付を受けることになった場合は、予定していた額が減るので「損した」と思ってしまうかもしれません。
そもそも医療保険は、入院などの万が一の時に「医療費が払えないと困る」とか「家計への影響を少なくしたい」という目的で加入しますので、還付額を気にするよりも自分が満足する保険給付が受けられることにフォーカスすべきです。
還付金の受け取り年齢は60歳以降であることが多いので、60歳以前ならば保険給付を受けないケースは多いかもしれません。
ポイント2「還付されるのは主契約部分のみ」
還付型医療保険で還付されるのは主契約のみというものが主流です。
一般的に特定疾病や先進医療などの「特約」は掛け捨てになっています。支払った保険料全額が還付されると思っている方にとっては、特約保険料分は還付されないことがほとんどなので確認が必要です。
それ以上に気になるのは、保険の見直しがしにくくなる可能性があることです。
昔に比べて入院日数が短期化したり、技術が進化したり、医療の変化に合わせて保険も変化しています。
最新の状況に合わせた保険の見直しをしようとした場合に、還付型医療保険を早期解約すると総支払額より還付額が少なく損をしてしまいます。
また、主契約を解約してしまうと特約もなくなってしまいます。
しかし主契約は残し、特約だけ解約して見直すならば還付額に影響はありません。
なので、見直しをする場合は還付型医療保険の主契約を残して、新たな保険を追加するケースが多くなります。
ポイント3「保険料払込満了まで割高な保険料を払う」
最初の方のシミュレーションのとおり、還付型医療保険は、掛け捨て型医療保険に比べて割高です。
加入した当初は負担感を感じなかったものの、住宅購入や教育費準備が家計の項目に入ってくると保険料負担が重く感じる方も多いです。
現金が必要な場合に引き出すことができず、契約者貸付という制度があるものの還付金給付年齢前では借りられる金額も多くありません。そのためにローンを組むことになったら本末転倒です。
還付型医療保険は、保険料払込期間まで割高な保険料を払っていける方向けの保険と言えます。
還付型医療保険に向いている人
還付型医療保険に向いている人の特徴をまとめてみました。
- 保険料払込満了まで割高な保険料を払っていける方
- 保険給付を受けた場合は、保険給付額が還付額から差し引かれることを理解したうえで「保険料が戻ってくる方がいい」と思う方
- 保険料が割安な掛け捨て型医療保険との差額を「運用した方がお得かもしれない」ということが腑に落ちない方
家族全員還付型医療保険に入っている場合は、月々の保険料の額もそれなりに大きな金額になると思われます。
FP相談の現場から
支払った保険料が戻ってくる還付型医療保険は、保険セールスマンにとっては販売しやすい保険です。
「掛け捨てではない」というワードが、極端な損失回避傾向のある日本人にマッチしているからです。
掛け捨て医療保険との保険料差額を運用する方がお得になる可能性があることをお話しした場合、つみたてNISA経験者の方はストンと腹落ちして下さる方が多いです。
「お孫さんの医療保険を払ってあげたい」というおじいちゃんおばあちゃんにとっては、還付金をプレゼントすることができるので、それはそれでアリだと思います。
(私も実際そのようなプレゼンをしています)
損得よりも、まずはライフプランを通して「保険料を払込満了まで払っていけるのか」を考えることがポイントです。